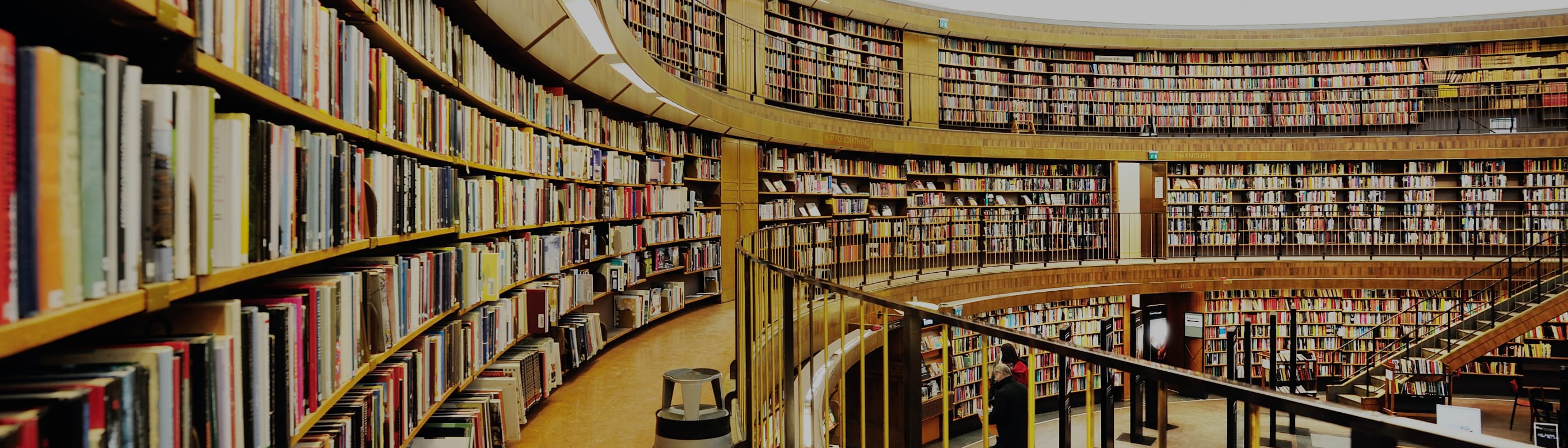認知戦の動向変化と金融事業者への影響(第13回)
コラム認知戦とは何か:定義と進化
認知戦(コグニティブ・ウォーフェア)とは、人間の認知領域、つまり「精神状態」や「行動」を標的にし、相手の意思決定や世論形成を自分に有利な方向へ誘導する戦略的な情報戦です。もともとは軍事分野での情報戦の一部でしたが、近年のインターネットやソーシャルメディアの普及により、認知戦が独立した重要領域として急速に発展しています。特にAI技術の進歩によって、ディープフェイク(AIによる精巧な偽動画・偽音声)やボットネットを活用した大量の偽情報拡散が容易になり、現代の認知戦はかつてない規模と速度で展開されるようになりました。実際、ロシアによる2016年米大統領選介入や、中国が台湾世論を揺さぶる試みなど、国家戦略の一環として認知戦が活用されています。民主主義国家では言論の自由ゆえに情報が拡散しやすく、認知戦の脅威が特に高いと指摘されており、日本でも防衛省が2023年度から本格的な認知戦対策に乗り出すなど、各国がこの新たな脅威への備えを進めています。
金融業界を脅かす認知戦の実例
認知戦の潮流は金融業界にも直接的な脅威を及ぼしています。国内外の事例からそれを見てみましょう。
- 昭和期の取り付け騒ぎから令和のSNS銀行危機へ
1973年、愛知県の某信用金庫で女子高生の雑談が発端となったデマが広がり、「理事長の自殺」「職員の横領」といった根拠なき噂に発展しました。その結果、2週間足らずで14億円もの預金が引き出され、信用金庫が倒産の危機に陥ったのです。この昭和の事例は口伝えの噂でしたが、SNS時代の現代ではさらに拡散力が増しています。実際、2023年に米国シリコンバレー銀行(SVB)が経営破綻した際、SNS上の不安拡大が預金流出を加速させ「SNSによる初の取り付け騒ぎ」とまで評されました。わずか24時間で420億ドル(約5.6兆円)の預金が流出したとの報告もあり、金融当局もこの新たな危機に強い警戒感を示しています。 - AIディープフェイクを悪用した詐欺
金融分野ではサイバー犯罪者も認知領域への攻撃を仕掛けています。例えば香港では、AIによる顔交換(フェイススワップ)技術で企業幹部の顔と声を偽造し、ビデオ会議で経理担当者を巧みに騙して香港支社の資金を不正送金させる事件が起きました。被害額は約2億香港ドルにも達しています。このような高度ななりすまし詐欺は従来のセキュリティ対策では発見が難しく、金融機関の信頼性と財務に深刻な打撃を与えかねません。 - AI生成デマによる市場操作のリスク
ソーシャルメディア上でAIが生成した偽ニュースや偽の金融情報が広がれば、株価や為替を人為的に動かす相場操縦も可能になります。実際、英国の調査ではAI生成の偽情報記事や偽のミーム(ネット上の風刺画像)を銀行顧客に見せたところ、3分の1が「極めて高い確率で」預金を移すと回答したとの報告があります。わずか数十ドルのSNS広告費で何百万ポンドもの預金流出を誘発できる可能性が指摘されており、金融セクターにおける認知戦リスクは急速に高まっています。
以上の事例は、情報操作や偽情報が金融機関に実害を及ぼす現実を示しています。中堅・中小の金融事業者も例外ではなく、むしろ限られたリソースゆえに標的にされやすい点に注意が必要です。
地方金融機関の脆弱性(PEST視点)
中堅・中小の銀行、信用金庫、保険会社といった地方金融機関は、大手に比べ認知戦への耐性が十分とは言えません。その脆弱性をPESTの観点で整理します。
- 政治(Political)
国家間のサイバー紛争や情報戦の余波を受けやすい立場にあります。政府レベルのディスインフォメーション(偽情報)工作が国内に波及した場合、地域経済の要である地方金融機関が混乱の標的になる恐れがあります。また規制当局からのガイダンスや支援体制も整備途上で、明確な対応策がない中で対応を迫られるリスクがあります。 - 経済(Economic)
大手金融機関に比べサイバーセキュリティや広報対応に割ける予算が限られています。不安噂による一時的な預金流出でも経営基盤が揺らぎやすく、特に地域のメインバンクとして信用不安が広がれば地元経済全体に波及する危険があります。さらに、AI偽情報を使った相場操縦により保有資産の価値が急変するなど、市場リスク管理面でも脆弱です。 - 社会(Social)
地域密着の強みと表裏一体で、地域社会で流布する噂やSNS投稿の影響を強く受けます。高齢者を含む顧客層ではデマ情報への免疫が低く、悪意ある情報が流れた際にパニックに陥りやすい傾向があります。先に挙げた愛知県の信金事件が示すように、誤情報が一度地域コミュニティに浸透すると、鎮静化に時間を要し信頼回復が困難になります。 - 技術(Technological)
ディープフェイク検知やSNS監視といった最新技術の導入が遅れがちです。サイバー攻撃への防御態勢も限定的で、AIを駆使した新手法による標的型フィッシングやなりすましに気付けない恐れがあります。オンランバンキングの浸透で預金移動が数秒で可能になった現在では、偽情報による瞬間的な取引集中にシステムや対応が追いつかないリスクもあります。
以上のように、地方金融機関はリソース不足や地域特性からくる脆弱性を抱えており、認知戦の観点から多角的な対策を講じる必要があります。
認知戦に備える戦略的アクション
認知戦の脅威に対し、経営層が取るべき対応は待ったなしです。単なるIT対策に留まらず、ガバナンスから現場教育、社外連携まで包括的な戦略が求められます。以下に具体的なアクションプランを提言します。
- ガバナンス強化
取締役会や経営会議で認知戦リスクを正式な議題とし、経営リスクの一種として位置づけます。情報戦への備えを含めたリスク管理ポリシーを策定し、緊急時の対応フロー(例えば悪質なデマ発生時の広報手順)を明文化しておきます。 - 監視と早期警戒
自社や地域に関するSNS上の言及をモニタリングする体制を構築します。不審な噂や急激な風評の拡散を検知したら、早期に事実関係を確認し必要に応じて迅速に声明を発出します。また、サイバーインテリジェンス企業や専門機関と提携し、海外発のディスインフォメーション動向について定期的な情報共有を受けるのも有効です。 - 社員教育と顧客啓発
内部的には、役職員に対してソーシャルエンジニアリングやディープフェイクに関する最新手口を学ぶ研修を実施し、怪しい情報への対処法を周知徹底します。加えて、顧客に対してもニュースレターやセミナー等で金融詐欺やデマへの注意喚起を行い、地域全体のメディア・リテラシー向上に寄与します。特に高齢顧客には窓口で声掛けするなど、Face to Faceでの啓発も検討します。 - 技術とプロセスの導入
ディープフェイク検知ソフトや異常な取引パターンをリアルタイム分析するシステムの導入を検討します。また、電話やオンライン会議で重要指示を受ける際には複数担当者による確認プロセスや本人確認の二要素認証を課すなど、騙されにくい業務フローを整備します。テクノロジーと人間のプロセス両面で多重防御を築くことが重要です。 - 外部連携
危機対応においては警察や金融庁、日本銀行など規制当局との連絡経路を平時から確立しておきます。万一デマが発生した際には速やかに相談し、必要に応じて共同で記者会見や公的発表を行ってもらうことで沈静化を図ります。また他の地域金融機関とも情報共有ネットワークを作り、怪しい兆候や新たな攻撃手口を互いに通知し合うことで早期警戒網を張ることができます。
経営層自らが先頭に立ち、以上のような多面的対策を講じることで、認知戦時代における金融機関のレジリエンス(危機対応力)を高めることができます。認知戦への備えは単なる防御ではなく、顧客の信頼と地域経済を守る攻めの経営戦略とも言えます。情報が武器になる時代だからこそ、金融事業者は「人の認知」を守る新たな視点でリスク管理と経営判断を行うことが求められているのです。
※本内容の引用・転載を禁止します。