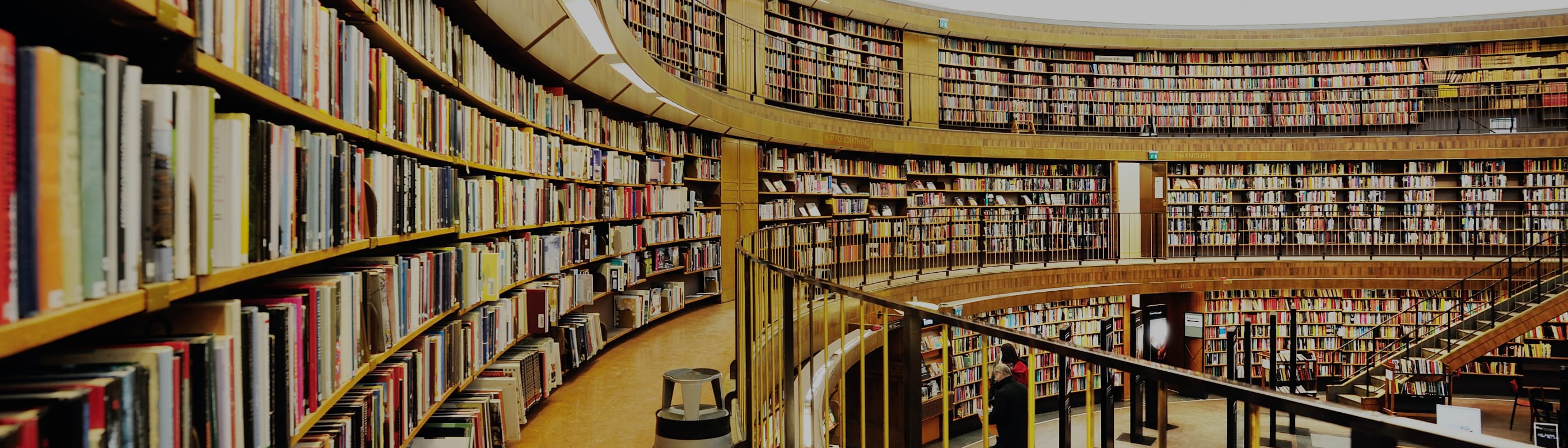内部不正対策こそ、未来を守る最前線(第11回)
コラム今日、企業が直面する脅威の中で、内部不正は外部からのサイバー攻撃以上に厄介で、発見が遅れた場合の被害拡大リスクが極めて高い問題です。特に金融機関では、顧客情報や取引データという極めて価値の高い資産が狙われ、内部統制の不備が大きな損失や信用失墜を引き起こす恐れがあります。金融業界では行員が顧客情報の改ざんや虚偽書類による不正融資審査をするような事例があり、また別のケースでは内部の不正アクセスによって顧客口座から多額の資金が不正送金されるなど、内部不正の深刻さが報じられてきました。
内部不正の新たな実態と脅威
内部不正とは、本来信頼されるべき内部関係者が、その正規の権限を悪用して不正行為を行うことです。かつては現金の横領や書類の改ざんなどアナログ的手法が主流でしたが、デジタル化の進展により、現代の内部不正はITシステムやクラウドサービスを狙った高度な手口に進化しています。たとえば、パスワードの使い回しや退職者のアカウント放置といった基本的な管理の不備に加え、リアルタイムのデータ監視を巧妙に回避する手法や、AI検知の盲点を突くためのデータ細分化など、攻撃者は常に次の一手を模索しています。私自身、多くの現場でこれらの新手法に直面し、そのたびに従来の対策では不十分であることを痛感してきました。
なぜ金融機関は内部不正の標的となるのか
金融機関は、莫大な顧客情報と取引データという高付加価値資産を保有するため、内部不正の狙い目となります。さらに、内部システムへのアクセス権を有する従業員や管理者の権限管理が不十分である場合、たとえばパスワードの再利用や退職者のアカウント削除の遅れといった問題が、不正行為を容易にしてしまいます。また、BYOD(Bring Your Own Device:従業員が自分所有のスマートフォンやタブレットなどを業務に利用すること)やリモートワークの普及により、モバイルデバイスやクラウドサービス経由での情報持ち出しリスクも急増しており、組織の成長とともにセキュリティの抜け穴は拡大する一方です。現場での対応経験から、こうした環境変化に迅速に適応できる体制整備が急務であると感じています。
経営層が取るべき具体的対策
内部不正対策は一朝一夕で構築できるものではありません。しかし、段階的かつ体系的な対策の実施により、大きなリスクを大幅に軽減することが可能です。特に金融機関では、次の5つのポイントに注力すべきです。
- ゼロトラスト・セキュリティの導入
すべてのアクセスを「信用しない」前提で管理し、各従業員に固有のIDを付与、不要な権限を徹底的に削減します。さらに、多要素認証(MFA)の徹底により、認証情報の悪用リスクを劇的に低減します。現場では、このアプローチにより、不正アクセスの試みを未然に防いできた実績があります。 - ネットワークのマイクロセグメンテーション
ネットワークを業務や部門ごとに細分化し、各セグメント間の不要な通信を遮断。万が一内部不正が発生しても、被害の拡大を効果的に防止します。実際、細かなセグメント化が早期の被害局限に貢献した事例もあります。 - SIEM/UEBAによる行動監視の強化
各種システムのログ(操作記録)を一元管理し、通常とは異なるアクセスや操作をリアルタイムで検知します。「SIEM(Security Information and Event Management)」は、サーバーやネットワーク機器から集約される膨大なログ情報を自動分析し、異常を即座にアラートするシステムですが、「UEBA(User and Entity Behavior Analytics)」は、従業員やシステムの通常の行動パターンを学習し、異常な動きを検出する技術です。これにより、内部不正の兆候を早期に把握し、迅速な対応が可能となります。私の経験から、これらのツールを適切に運用することで、未然に不正を防ぐ事例が数多く確認されています。 - 特権アクセス管理(PAM)の徹底
高権限アカウントに対しては、パスワード金庫の利用、セッション記録の徹底、定期的な権限見直しを実施。万一の不正操作時に速やかに対策を講じる体制を構築します。 - 従業員教育とセキュリティ文化の醸成
技術対策だけでは内部不正を完全には防げません。定期的なセキュリティトレーニング、フィッシング対策の啓発、内部通報制度の整備により、全社員が自らの行動を「自分事」として認識する意識向上が不可欠です。私がこれまで数多くの現場で見たのは、従業員の意識改革が内部不正リスクの低減に直結するという事実です。
専門家としての助言
ITやデジタル化は業務の効率化や顧客サービスの向上など、計り知れない恩恵と利便性をもたらしています。しかし、その恩恵の裏側には、内部不正などの新たなリスクが潜んでいるという現実があります。すなわち、先進のシステムやデジタル技術の導入が進むほど、その分だけ内部統制の抜け穴や不正行為のリスクも増大するのです。「より良い未来を手に入れるための投資」としてITを活用する一方で、潜在的なリスクの管理にも同等のリソースを割かねばならない、これは経営者にとって避けられないバーター(交換条件)なのです。
テクノロジーの急速な進化とともに、攻撃者は日々新たな手法を編み出しています。したがって、セキュリティ対策は一度整備して終わるものではなく、常に最新の対策を講じ、継続的に改善する必要があります。「安全は偶然の産物ではない」という信念のもと、今こそ内部不正対策に本腰を入れる時です。対策実施にかかるコストは、内部不正による取り返しのつかない損失や信頼の喪失と比較すれば決して高くありません。経営層のリーダーシップのもと、現場と密接に連携しながら、堅牢なセキュリティ体制を築くことが、企業の存続と持続的成長の鍵を握ると私は確信しています。
※本内容の引用・転載を禁止します。