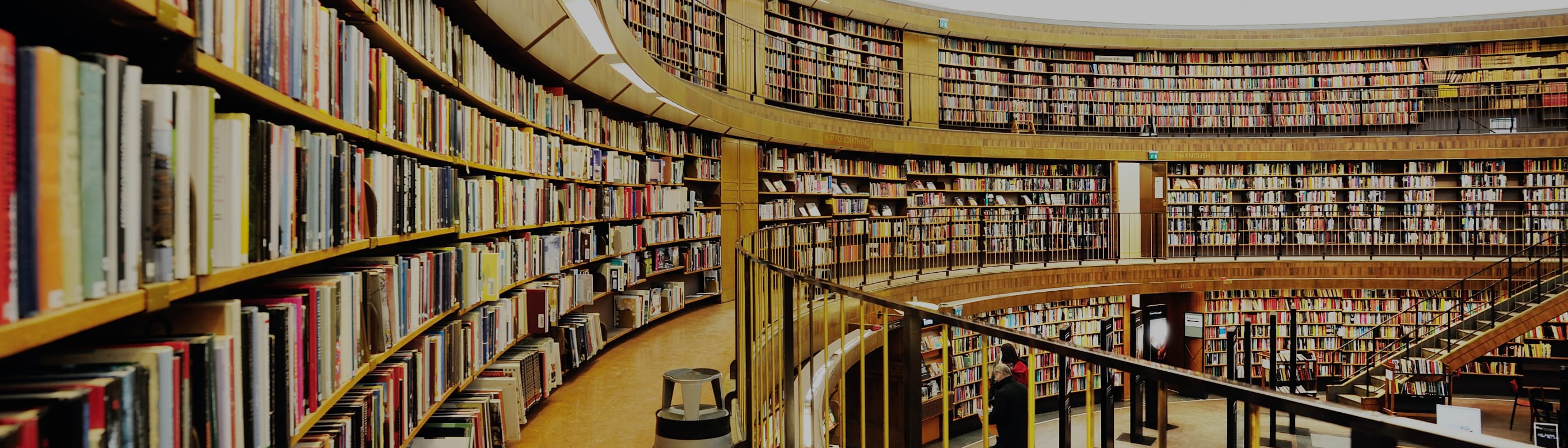〔変化をチャンスに 〜 変化を捉える視点と思考 〜〕
第62回:AI浸透後に広がる社会を妄想する(8)
コラム
<はじめに>
先日、若者と話をする機会があった。
「ツーブロックやポニーテール禁止」
今でもこんな校則を定めている学校があるらしい。ホントか?(笑)
「女子のタイツ着用禁止」「ダウンジャケット・マフラー禁止」
先日、日本は最強寒波に襲われた。生徒たちは、どう乗り切ったのだろう。
「部活動中の水分補給禁止」
これはどうだろう。昔はそんな部活も多かった。今の時代、熱中症リスクも指摘され、むしろ水分補給は推奨されるべきではないだろうか。
学校に限らず、社会にはいろんな常識や規範がある。多くの人は言われた通りに受け入れ、それに従う。たまに反発する人もいるが、反論したり、暴れたりする人たちは白い目で見られることが多いようだ。※私は後者だった(笑)
さて、ちょっと考えてみたい。
● 先人の言葉を受け入れ、従うことが「正しい」「良い」ことなのだろうか
● 先人の言葉に疑問を呈することが「間違っている」「悪い」ことなのだろうか
日本には素直で従順な人が多いと言われる。会社の命令に従い、上司からの指摘を受け入れる。学校教育の影響(成果?)なのか、それらしい言葉には、疑問を持たずに忠実に従うことを是とする人が多いように感じる。これは、気のせいだろうか。
上記は「AIと向き合う力」の話につながる。例えば、生成AIの出力をどう受け取るか。どれだけ「生成AIが間違った答えを出力することがある」と言われても、生成AIの出力をレポートに貼り付けてくる学生は後を絶たない。実は、この問題は根が深い。情報の認知プロセスから考察する必要がありそうだ。
今回は、AI浸透後の社会に我々人間がどうあるべきか、どう変わるべきかを考察する。
<制脳権と認知戦の時代>
前回(第61回)、制脳権と認知戦について紹介した。世界は物理空間、サイバー空間に続いて、認知空間を次の戦略領域と捉えている。洋の東西を問わず認知戦、すなわち、制脳権の奪取や人の脳や思考を標的とする戦争が浸透しつつある。マスメディア、著名人の発言、SNSなどを使って大衆の思考を操作する情報戦が広く展開されている。
今後、生成AIが認知戦で重要な役割を果たすことも紹介した。我々人間が生成AIに接する時間が増えるほど、必然的に、その役割は大きくなる。
問題は「そのときに我々人間がどうあるべきか」である。認知戦の時代、重要なのは人間の認知プロセスである。情報をどう受け取るか、そこから何を考えるか、そして、何を発信するのか。
以下では、認知プロセスの視点から議論したい。
<AI浸透後の社会を見据えて>
AI浸透後の社会に向けて、我々にはどんな能力が求められるのだろうか。今後、AIはさらに進化・浸透していく。AIを介して、様々な情報、知識、さらには思想・哲学に触れることになるだろう。そのとき、すべてを鵜呑みにするだけでは能がなさすぎる。認知プロセスの刷新が必要になるのではないだろうか。
まずは、最もシンプルな認知プロセスについて整理しよう。
● 入力(input):情報を受け取る
● 処理(process):受け取った情報を理解・記憶する
● 出力(output):自分の知識から、常識・正解を選んで発信する
「正解がある時代」には上記が通用した。学校教育の教科書、社会人教育の研修を思い返してほしい。「正解」であることを前提に提供される情報は「疑うことなく」インプットされる。さらに、効率を背景に、必要最小限の情報を「選別することなく」すべてを理解・記憶する。常識・正解と思われるものを発信するのは「忖度」に通じるものがある。
「正解がある時代」の認知プロセスは、認知戦に対して極めて脆弱である。教育、メディア、SNS、そして生成AIにいたるまで、情報を鵜呑みにするのは危険すぎる。例えば、メディアが伝える内容をそのまま受け取り、理解し、伝播しているようでは同調圧力の形成に加担しているに等しい。生成AIの利用についても同様である。
今は「正解のない時代」と言われる。言葉や距離の制約から開放され、国境の概念さえ薄まりつつある。多様な価値観が共存し、社会は正解のない問いに溢れている。何が正解か、ではなく、自分がどう考えるか。価値観や哲学が認知プロセスの前提として求められる時代になった。
これからの認知プロセスはどうあるべきだろうか。本稿では、AI浸透後の社会に向けて、我々人間が認知プロセスを刷新することを提唱したい。
● 入力(input):(受け取るだけではなく)多様で多彩な情報から、大事なものを見つけ出し、気付きを得る。同時に違和感を感じる力も必要。
● 処理(process):(理解・記憶するだけではなく)思考・熟慮し、抽象化を通してモノゴトの核心を射抜く。また、言語化を通して参照・再利用可能にする。
● 出力(output):(常識・正解を探すだけではなく)自らの考えや価値観を自分の言葉で表現し、その本質を伝える。
必然的に教育も変わる必要がある。今の学校教育・社会人教育は「正解がある時代」の認知プロセスが主になっているのではないだろうか。今後は「正解のない時代」の認知プロセスを養うための仕組みが必要になるだろう。
AI浸透後の社会に向けて人間も変わる必要がある。特に、認知プロセスは、何にも優先して身につけたいものだと思うが、どうだろうか。
<終わりに>
■本稿は第55〜61回の続編である。主テーマは
「今の生成AIで何ができるか」ではなく
「AI浸透後に社会がどう変わるか」である。
その前提にあるのは、何度も紹介している次の視点である。
● ”What” を変えず “How” の変化を考える「深化」
● ”Why” に立ち返って変化の先の “What” を考える「探索」
本連載は「探索」の視点で考察する。生成AIに大きな可能性を感じている方は多い。「今の生成AIをどう使うか(深化)」ではなく「その先に社会がどう変わるか(探索)」を考えることで、その可能性のイメージが広がるのではないだろうか。
今回は、前回の議論を受けて、生成AIと(さらには、次のAIと)つきあうための心構えを考える回とした。今後、様々なAI技術が登場することは間違いない。そのときに、我々人間がどうあるべきかを考えるヒントになれば幸いである
※本内容の引用・転載を禁止します。