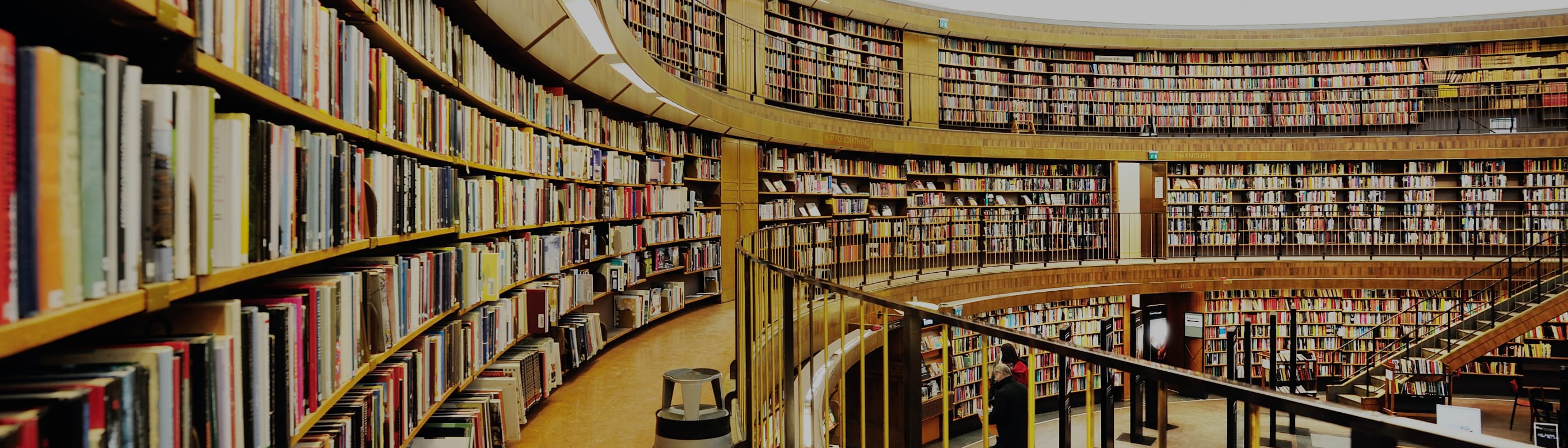〔変化をチャンスに 〜 変化を捉える視点と思考 〜〕
第60回:AI浸透後に広がる社会を妄想する(6)
コラム
<はじめに>
「教科書」は凄かった。(過去形、なのか? 笑)
※勉強が嫌いだった自分にとって、教科書に良い思い出はないのだが(笑)
学校教育では教科書を使う。少しずつの改定はあるものの、毎年義務教育対象者で一千万人近くがほぼ同じ内容を勉強する。それも、何十年と続けられてきた。日本の全国民に一律共通の内容を教えようという試みは、考えてみるとスゴイなのかもしれない。(*1)
(*1) このことは、本稿の後半で考察する
今、我々は転機を迎えている。生成AI(もしくは、その次のAI技術)は教育のあり方を変える可能性がある。これまでの教育は、印刷物である「教科書」を主としてきた。遠くない将来、AIとの「対話」が教育の中心になりえる、とは感じないだろうか。
AIが教育を担う時代が来るかもしれない。生成AIは急速に進歩している。膨大な(教科書の内容を含む)形式知を学習済みで、かつ自然な対話が可能な技術が目の前に広がっている。それが教育の世界に浸透していくと考えるのは納得感があるだろう。
今回は、AI浸透後に広がる社会で「教育がどう変わっていくのか」を妄想してみたい。
注目すべきは、AIが教育のカタチをどう変えるか、である。技術革新が教育にもたらした変革を参考にしつつ、直面するAI革命が教育にもたらすインパクトを考察してみよう。
<活版印刷と教育>
今回は「活版印刷」について考察しよう。印刷技術の起源は諸説あるが、ヨハネス・グーテンベルクの話は有名だろう。彼は、1445年頃に聖書を印刷したとされる。その後、活版印刷技術は急速に普及し、ルネサンスの三大発明の一つと言われるようになった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/活版印刷
https://tplant848.com/blog/letterpress-printing-history
活版印刷は教育のあり方を大きく変えた。活版印刷の普及は書物を流通させ、文化の浸透にも大きく寄与した。結果的に庶民の識字率が向上し、やがて印刷物による教育が広まったことには疑いの余地がない。
※考えてみると、印刷技術普及以前、人々は、どんな「教育」をしていたのだろう(笑)
さて、
活版印刷は何がスゴかったのだろうか。
印刷技術は「言葉と知識の外部化」をもたらした - ある人の言葉が印象的だった。従来、言葉や知識は人に依存していた。印刷技術は言葉と知識を大衆化させたのだという。
印刷技術が国の概念を変えたという説もある。印刷技術の登場以降、言葉や知識が広範囲かつ永続的に伝播・伝承できるようになった。その結果、同じ言葉を話し、同じ知識を有する人たちが同じ国に属すると考えるようになったと言われている。
考えてみると、冒頭の話 (*1) も理にかなっているのかもしれない。教科書があることで、全国民が同じ言葉を話し、同じ知識を有することになる。それが「国」を形成する上で重要な役割を果たしていたのかもしれない。(その内容については賛否両論ありそうだが、笑)
<AIと教育>
生成AIの登場は衝撃的だった。遠からず、次のAI技術も登場するだろう。既に仕事でAIを活用している人も、あるいはAIによって仕事が置き換わりつつある人もいる。だが、社会変革は始まったばかりだ。今後、さらなる激変が待っていることは間違いない。
ところで、
AIがもたらす変化の本質はどこにあるのだろうか。活版印刷がもたらした変化の本質を「言葉と知識の外部化」と表現した。言葉も、知識も、記録された静的なものとして保存・参照された。では、AIがもたらす変化の本質は?
今後「対話と見識の外部化」が進む - 我々の研究グループではこのように考えている。これまで対話は人間特有のスキルだと思われていた。見識は人の価値観が反映された知識の捉え方だとされてきた。それが外部化される可能性がある。
既にAIはネットの向こう側にいる。相手にあわせて(知的レベルや興味関心にあわせて)自在に「対話」する。立場や価値観にあわせて知識の解釈を使い分けることで「見識」を披露してくれる。今現在の生成AIはいくつかの課題も指摘されているが、やがて、その課題を解決する次のAIが登場する日が来るのだろう。
今後、AIが教育を変える可能性は大きい。知識量はいうまでもなく、思考や推論の能力も高い。一人ひとりにあわせた対話を通して、その知識や能力にいつでも触れることができる。しかも、一律共通な価値観を押し付けるのではなく、多様性を前提に様々な立場を理解して接してくれる。
もしかすると、教育の考え方そのものが変わるのかもしれない。いや、むしろ、教育が(良い方向に)大きく変わることに期待したい。
※少なくとも「生徒が生成AIを使う」という次元の話ではないことは明らかだろう。
<AI浸透後の教育を考えるうえで大事なこと>
今回は、AI浸透後に広がる社会で「教育がどう変わっていくのか」を妄想してみた。対話と見識の外部化が教育のあり方を根本的に変える、という考え方は大胆かもしれないが、AIが教育環境に深く浸透するのは容易に想像できるだろう。
ひとつ大事なことがある。前回(第59回)も書いた通り、AIには個性や性格があるということだ。さらには、そのAIが学習した知識の偏りも気になる。自分の子どもや孫が教育を通して触れるのはどんなAIなのか。これが、とても重要な視点になることに留意したい。
もうひとつ大事なことを追記しておく。AI浸透後には、教わる内容も変わる必要がある。今年生まれた子どもたちが社会に出るのが20年後だと考えると、教わるべきは、今の教科書に書かれている内容ではなく、20年後に必要な知識であり、見識であり、能力だろう。悩ましいのは、その内容なのだが。
※いったい、誰が、どうやってその内容を決めることになるのだろうか…
AI浸透後の社会に向けて教育は大きく変わっていく。必然的に、そこには大きなビジネスチャンスがある。教育はどうあるべきか。教育をどうしていきたいのか。AIの浸透を前提に深く考えてみたいテーマである。
<終わりに>
本稿は第55〜59回の続編である。ここまで考えてきたことは
「今の生成AIで何ができるか」ではなく
「将来、AIがさらに進化・浸透したときに、社会がどう変わるか」である。
その前提にあるのは、何度も紹介している次の視点である。
● ”What” を変えず “How” の変化を考える「深化」
● ”Why” に立ち返って変化の先の “What” を考える「探索」
本連載では「探索」の視点で考察する。生成AIに大きな可能性を感じている方は多い。「今の生成AIをどう使うか(深化)」ではなく「その先に社会がどう変わるか(探索)」を考えることで、その可能性のイメージが広がるのではないだろうか。
前回からの流れで、今回は教育について考えてみた。次回以降は、少し身近なところに目を移して、AI浸透後に何が起こるのかを考えてみたい。
※本内容の引用・転載を禁止します。